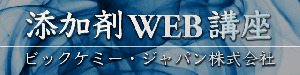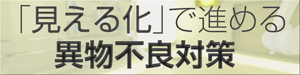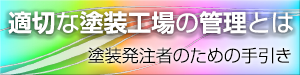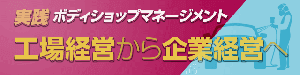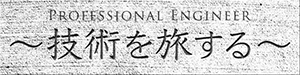●「塗装設備の選択」
塗装設備の仕様は被塗物の形状とその塗装範囲、使用塗料の種類、設備の自動化度合い、生産量などにより決まりますが、大企業社内の専用塗装ラインと電着塗装を除くと、次の2種類に当てはまると思います。その典型的な塗装工程の内容は下記のように考えます。
パターンA:溶剤型塗料が主体で塗料非回収にて自動水洗ブース+補正水洗ブースの工程。
溶剤塗装(一部水系塗料、一部粉体塗料)の自動塗装水洗ブース(レシプロケータ又は多関節ロボット使用)+補正塗装の水洗ブースで、人手作業により主に自動塗装の補完として、静電ガン又はエアーガンによる補正塗装をします。
※塗料は溶剤、粉体共に非回収で水系の一部では回収使用の事例もあります。
パターンB:粉体塗料が主体で塗料回収仕様にて自動ブース+補正ブースの工程。
粉体塗装の自動塗装ブース(レシプロケータ又は多関節ロボット使用)+人手による静電ガン補正塗装ブースで、同一塗料による生産量が多い場合は回収再使用し、少量使用塗料は非回収とします。非回収は水洗ブースで行ってしまう場合もあります。
※ただし前補正か後補正かはこだわりません。また、粉体塗装はセッティングが不要です。
※焼付け温度が異なる場合や、多色の塗料を使用する場合は混色、コンタミなどが問題となりやすく別設備での塗装が望ましくなります。
AとBそれぞれ、疎かになりがちな下記の留意点があると思います。
A:留意ポイント1 セッティングゾーンの確保
塗装後にセッティング時間が必要ですが、時間を必要最小限確保することが大切です。時間不足や焼付け炉からの影響でのセッティングゾーンの温度上昇は、塗料やシンナーの選択幅を狭め、塗膜品質を低下します。シンナーの選択幅を広げ、塗膜レベリングに僅かでも余裕を持たせることが大切なゾーンです。
A:留意ポイント2 水系塗料には特化した設備が必要
水系塗料は溶剤型塗料に比べ、塗膜形成が塗装ブースの温湿度に影響される場合が多く、焼付け乾燥も予備乾燥が望ましい事例が多いと思われ、本格的に水系塗装に特化した設備設定のためには、予備乾燥の必要性について事前に綿密な塗装テスト、塗膜状態の確認などが必要でしょう。セッティングについての考え方は溶剤型塗装系と同様でしょう。
B:留意ポイント1 メイン色があれば回収効果大
粉体塗料は1回目の塗装で被塗物に塗着しなくても、回収再使用が出来る大きな利点があります。逆に言えば、主力と言える生産量の多い色の塗料がないと回収再使用の採算性が低くなります。端的に言えば回収可能な生産量がある塗料を使用する機会がないと回収設備を備えても儲かるチャンスが少ないと言わざるを得ません。
B:留意ポイント2 粉体塗料といえども作業環境に配慮は必要
粉体塗料は確かにシンナーを使わないのでVOCがほぼ0です。しかし、時折見かける補正塗装作業者の極端な塗料まみれの姿は「健康的には程遠い」としか見えません。そのため作業環境改善は絶対必要です。
上記のAとBは一般的にどのような被塗物形状でも実績としても数多く見かける塗装工程です。従って、特異な形状(長尺もの、複雑形状もの等)の被塗物は寸法的な対処や塗装法により適用対応となりますが、将来の見通しに運・不運もあるでしょう。
これからは、我が工場が唯我独尊ではなく、例えば距離的にも近い範囲でそれぞれに特徴を持つ工場が仕事を分け合う「緩い団結」又は「シェアする」中で塗装を受合うことにより、変化が速い時代での「儲かる塗装」にありつく1つの方法ではないかと思います。(1工場での減価償却がなし難くなるのではないかとも思います)
●塗装設備運用の注意点
① 「前処理後はすぐに塗装へ!」
前処理を施した被塗物を出来るだけ速く塗装すべきであることは誰でも承知しています。化成皮膜は薄い敏感な皮膜であるため、化成処理の状態で翌日(又は連休明け)までそのままの状態では結露や塵埃などの影響を受けやすく、原則として当日に前処理+塗装までを完成させる場合は安心できますが、それほど「悠長な」ことは出来ない工場が多いようです。
仕掛品置き場の雰囲気が問題ですが、結露(又は化学的雰囲気)の可能性が短時間でもある場合は設備的な改善をしなければなりません。
ただし、塵埃などの影響を避けての(簡単なカバー掛けなど)翌日持越し程度は止む負えない対応と判断される場合が多いと思われます(塗装後の品質として問題ないことが確認されていることが前提ですが)。
休み時間中の前処理設備、塗装設備中の一時停止も実績を確認してから、その設備ごと又は被塗物素材ごとに判断するのが現実的と思われます。
② 「各工程における意思疎通が大切!」
セッティングゾーン+焼付け完了までは、塗装外観の仕上がり状態を明確に目視確認できないいために自動塗装と手吹き補正塗装の微妙な調整判断が出来ない場合があります。最悪の場合、焼付け炉を出て冷却中に被塗物表面を目視確認して、「外観不良」となった場合、工程中の被塗物も「不良」となります。
IoT関連の信号、AI関連ロボットやセンサーなどを駆使しても「ゆず肌」「スケ」等の微妙な判断は容易にできません。インターホンなどで人の声と表現により、不良品の山を造らない迅速な対応が大切です。つまり、自動塗装操作、補正塗装各々担当者と検査担当者の緻密で迅速な(人と人との)伝達が必要な場合があります。
③ 「粉体塗装は誰でも簡単にできる?」
よく粉体塗装は熟練工が不要と言われます。確かにワキやタレ不良は出難く、極端な柚肌塗膜にもなり難いとは思えますが、やはり丁寧にデータに基づく塗装設定をしないと無駄な厚膜塗装や極端な柚肌にもなります。極端な印象を与えるような安易な言葉は止めた方がよいと思います。もちろん、各工場においては作業の標準化や新人教育の大切さは分かっておられることですから、その点の抜かりはないでしょうが。
④ 「特定エキスパートへの依存は避ける!」
塗装作業や不良品再生作業には経験の長さだけではなく、個人のセンス、器用差、応用感覚などに個人差が有るのが当然です。それを少しでも抑えて「誰がやっても大差ない」様に作業の標準化を進め、QC工程表範囲内の品質範囲を堅持して良品を造るわけです。この体制を維持するために大切なこと、即ち「生産性を向上しコストを下げるために」1人の名人作業者をつくるのではなく、複数の多能工化、兼任化が必要です。特定の作業者の存在で製品品質が左右されてはいけません。
⑤ 「ハンガー設計がコスト削減に影響!」
塗装工場内の設備や治工具は社内製と社外調達したものがありです。従って、作業性を良くしたり、消耗材料や薬品の使用効率を向上させたりすることには格差があります。防音壁や安全柵、空調範囲を狭くして費用を低減する工夫にも出来・不出来があり、作業環境や空調コストにそれぞれ影響を与えております。レイアウトの工夫は工場全体の見通し管理にも影響しコスト、安全、生産効率等の決め手になります。
そこでハンガーはどうでしょうか?この工夫度合いが塗装当事者が自ら判断しなければならない最も大切な=コスト、品質、納期の決め手となる=仕事と思います。必ずしも自社製が好ましいわけではありません。多くの経験を持つ専門業者と相談するのも有効です。
大切なことは薬品、塗料、塗装、膜厚(分布を含む)、一定の塗膜性能等に注目し過ぎて、ハンガーの維持管理=塗膜が付き過ぎた部分の剥離法、被塗物適用範囲の共通化、被塗物脱着の容易化と着荷の確実化、非使用時の格納法、マスキング等が疎かにならないように、上記の各作業の関心度合いが偏らないことが大切であり、筆者の経験でもハンガーの設計と管理の熟練工がいると良い結果が出ている事例が多くあります。
⑥ 「日々のメンテナンスと適材適所の確認!」
設備・機器の保守管理は大切なのは分かっていてもつい後回しになるものです。そして大事な時に限って故障したりします。逆に言えば、普段から手入れが悪い設備を急いで動かせばガタが来ます。それは当然とも言えます。コンプレッサーや電源等が「風通しが悪い」「保守作業の場所が狭い」「暗い」「湿気が多い」場所にありませんか。保守管理、運転コスト、設備寿命等々いずれも不適切な事例が多く、エアー、蒸気の配管の腐食も気になる工場を多く見かけます。
更に細かく言えば、塗装不良再生のサンディング場所が塗装場に近過ぎ(塵埃多)、西日が当たる場所で検査やハンガー掛け外し(悪環境)、非使用ハンガーの屋外格納(塵埃)、汚れた作業服(糸くず)、床面始め工場内の汚れ(塵埃)等々、塗装不良の原因は沢山あり、それが日常化して、関係者が気にならなくなってしまっている恐ろしさがあります。筆者は意識改革のために「塗装工場内履物は工場外と分ける」提案をするようにしています。
⑦ 「塗料貯蔵の管理は"危険物"以外にも注意が必要!」
溶剤型塗料とそのシンナー類は法律の通り危険物倉庫中にて決まられた数量の範囲で貯蔵しなければなりません。水系塗料、粉体塗料についても塗膜品質や塗装作業に支障を来さないための、貯蔵期間、温度、積み重ね(加重)等の守るべき数値があるので、塗料メーカーや販売店等と十分に協議、確認の上貯蔵条件を決めて法規制を含めて守る必要が有ります。現実には基準の維持が困難な事情がありがちですが(特に塗料の在庫期間等)、例外を認める訳には参りませんので確実な履行が大切でしょう。