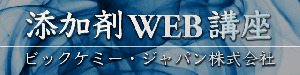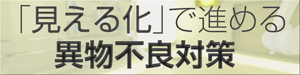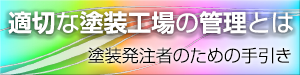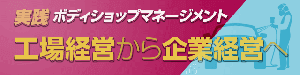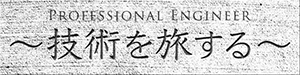こんにちは。今回から塗装実務に絡む周辺知識の話をします。私は金属部門で技術士を取得したので、主に金属に関する話です。知識の習得は主に製品から学びました。どんな素材・加工で製造されているか、調べるだけでも実務に役立ち、過去のトラブルと対策は応用面でも有効でした。手始めに素材編"鉄"です。
鉄と鋼の違いって何だろう?
我々塗装業者が図面を見るとき、一部の表面処理材や樹脂を除いて、素材は鉄、ステン、アルミなど、この程度の違いの認識で、実際事足りるのではないでしょうか?
現代社会の中で最も多く使用されている金属材料は鉄です。"鉄"といっても、普段我々が扱っているのはFe元素だけの純鉄ではなく、炭素や他元素との合金で、多くは鋼です。板金図面で良く見かける"鉄"の類はCC400(炭素鋼)、SPCC(冷間圧延鋼板)など、見ると"鋼"の字が付いていますね。主として炭素が性能に影響するので炭素の含有量で区別します。
鋼は炭素が鉄に対して限度2.14%まで溶け込んだ鉄との合金です。炭素の許容限度を超えたものは、鋳鉄となり、材料中に個体炭素が点在します。鋳鉄は「固いが脆い」性質です。主にマンホールや厨房コンロなど鋳造品で扱われます。
我々塗装業者が板金やプレス品で扱う鉄材は元素の鉄をベースに、炭素や他の元素の配合や熱処理で金属組織を調整し、使用用途に応じて工業生産された鋼です。
黒皮、スケール、酸化被膜
鋼材を前処理する際に気を付けているのは表面状態でしょう。黒皮、スケール、酸化被膜、これらは現場用語の違いで、ほぼ同類です。
鋼材の表面はもともと製造過程で熱せられた酸素と結びついて酸化被膜ができます。SPCCなど薄板は鉄鋼メーカーでコイルにする前に酸洗して酸化鉄を除去したものです。
ちなみに酸化被膜が酸化鉄であるのに対し、厄介な赤錆は水酸化物で水と酸素が結びついたものです。そのため、酸化被膜は進行しませんが、赤錆は鉄が空気中の湿気と反応し、膨張しながら進行します。(錆の話は、後日詳しく説明します)
実務では酸化被膜は、板金加工のレーザー等、溶断面でも発生します。この酸化被膜は、膜が薄いので、リン酸塩などによる化成処理をした際、酸と反応し脆くなります。塗装の際、網跡部分が被膜から剥がれることもあるので対策が必要です。
最近のレーザー加工では、クリーンカットと呼ぶ、液体窒素を吹き付け急冷することで、酸化被膜が発生しない技術が急速に普及しています。仕様調整には、クリーンカットをお願いするとよいでしょう。
次回は、素材編ステンレスについてお話しします。
1968年生まれ。1992年、中央大学理工学部土木工学科卒、同年、カーナビメーカーに入社、バードビュー表示や音声ガイダンスの開発に関わる。 1997年、家業の(有)小柳塗工所に入社。1999年、父親である先代社長の急逝により代表取締役に就任。2010年、これまでの技術経歴を生かすため、国家資格である技術士資格(金属部門)を取得、2012年には総合技術監理部門を取得。以来、中央大学理工学部の兼任講師、東京工業塗装協同組合理事、東京商工会議所墨田支部評議員の公職も務める。